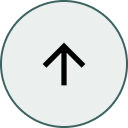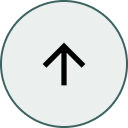調布歯科・かおいく矯正歯科では、歯並びを悪化させる根本的な原因に対してアプローチを行う新しい小児矯正歯科治療「顔育矯正」を実施しております。根本的な原因を取り除くため、治療後も後戻りしづらいのが特徴です。また、小児期は顎の成長過程にあるため、歯並びと共にお顔立ちにも良い影響を及ぼします。

ホーム » 矯正歯科治療 » 小児矯正(子どもの矯正歯科治療) – 顔(顎)の成長を育む顔育矯正 » 子どものすきっ歯は自然に治る?原因や治療法について解説
前歯にすき間がある「すきっ歯」は、まだ乳歯の子どもによく見られる症状です。
しかし、「自然に治るの?」「矯正が必要?」と心配している親御さんもいるのではないでしょうか。
この記事では、子どもがすきっ歯になる原因や自然に治るケース、放置することで起こりうるリスク、治療方法や治療開始の適切な時期についてわかりやすく解説します。
お子さんの歯並びを心配している方は、ぜひ参考にしてください。

いわゆる「すきっ歯」とは、歯と歯の間にすき間がある状態のことをいいます。
正式には「空隙歯列(くうげきしれつ)」または「歯間離開歯(しかんりかいし)と呼ばれる症状です。
特に前歯が「すきっ歯」であると目立ちやすいため、気になる親御さんもいらっしゃるかもしれません。
しかし、乳歯の時期には比較的多くの子どもに見られるものです。
成長段階における一時的な症状である場合がほとんどで、永久歯に生え変わる過程で自然にすき間が埋まるケースも少なくありません。
過度に心配する必要のないケースが多いでしょう。
ただし、中には永久歯に生え変わっても改善しない場合もあります。
そうなると、見た目が気になるだけでなく、発音や噛み合わせへの影響が出るリスクもあります。
治療の要否や方法は年齢やすきっ歯の原因によるため、早めに専門医に相談するのが望ましいといえます。

子どもがすきっ歯になる主な原因としては以下の7つが挙げられます。
以下では、それぞれについて詳しく解説します。
子どものすきっ歯は、乳歯から永久歯へ生えかわる時期に起こる一時的な現象であるケースも多いものです。
永久歯は乳歯よりも大きいため、生えかわりには乳歯期よりも広いスペースが必要です。
この時期にぴったり生え揃っていると、永久歯に生え変わった時にスペースが不足し、でこぼこの歯並びになる可能性もあります。
そのため、4〜6歳ごろの乳歯期のすきっ歯は問題ないケースも多いでしょう。
また、8〜10歳頃の乳歯と永久歯が混在する時期も同じ理由から、気にする必要がない場合がほとんどです。
犬歯が生えれば、隙間が埋まる可能性が高いでしょう。
いずれの場合も成長における自然な課程であるため、問題はありません。
歯とあごの大きさのバランスが悪いと、すきっ歯になる可能性があります。
たとえば、あごの大きさに対して歯が小さいと、歯と歯の間にすき間ができやすくなります。
逆に、歯が大きくあごが小さい場合には、歯が重なって生える「叢生(そうせい)」と呼ばれる症状になりやすいでしょう。
このような骨格バランスの問題は遺伝が原因の場合もありますが、成長の過程で変化するケースもあります。
矯正治療が必要になる可能性もあるため、早めに専門医へ相談するのが望ましいでしょう。
虫歯や外傷などが原因で、乳歯が本来の時期よりも早く抜けてしまうと、その部分にすき間が生じ、すきっ歯になることがあります。
実は乳歯には、後から生えてくる永久歯のスペースを確保する「ガイド」の役割もあります。
しかし、早期に失われてしまうと、周囲の歯がそのすき間に動いてしまったり、本来の正しい位置に永久歯が生えにくくなったりする可能性が高まります。
将来的に、すきっ歯になったり歯並びが乱れたりしやすくなるのです。
乳歯が早期に抜けてしまった場合は、「どうせ永久歯が生えてくるから」と軽視せず、歯科医に相談することが大切です。
「過剰歯(かじょうし)」とは、本来の歯の本数よりも多く生えてくる余分な歯のことをいいます。
歯ぐきの中に埋まったまま生えてこないケースも多く、そのために永久歯が正しい場所に生えそろいません。
歯と歯の間にすき間ができる可能性もあります。
特に上あごの前歯で起こりやすい症状です。
上唇小帯(じょうしんしょうたい)とは、上唇の内側と前歯の歯ぐきをつなぐ筋状の組織です。
赤ちゃんの頃は太くて長い状態ですが、成長とともに自然に後退し、目立たなくなります。
しかし、まれに退縮せず、太く長いまま残ってしまうケースがあります。
その結果、上唇小帯が前歯の間に入り込んでしまい、歯が寄りにくくなり、すきっ歯になってしまうのです。
上唇小帯を切除する外科処置が必要な可能性もあるため、なかなか退縮せず、隙間ができている場合は、早めに専門医に相談しましょう。
指しゃぶりや舌で前歯を押すクセ(舌癖)が原因になることもあります。
特に指しゃぶりを長期間続けていると、前歯が前方に押し出され、歯と歯の間にすき間ができやすくなります。
また、無意識に舌で前歯を押す癖も、同様に前歯を広げる力となり、すきっ歯を引き起こしやすいといえるでしょう。
こうした癖は、歯並びだけでなく発音やかみ合わせにも影響を及ぼすため、できるだけ早い段階での改善が望ましいといえます。
必要であれば、小児歯科や矯正歯科で行われるMFT(口腔筋機能療法)などの治療を受けるのも一つの方法です。
通常、人は、鼻で呼吸をすることで口の周りの筋肉バランスが保たれるものです。
舌は上あご全体に当たる位置にあります。
しかし、鼻詰まりなど何らかの理由で、常に口を開けて呼吸するようになると、口まわりの筋肉が十分に発達しません。
舌の位置も不安定になった結果、前歯に正しい圧力がかからず、すきっ歯や出っ歯といった歯並びの乱れにつながる可能性があります。

子どものすきっ歯は、成長に伴って自然に治るケースも多いものです。
そのため、乳歯から永久歯への生えかわり時期であれば、過度に心配する必要はありません。
この時期には、あごの成長や歯の大きさの違いによって一時的にすき間が生じることがよくあります。
すきっ歯であっても、永久歯が生えそろう10〜12歳頃には自然にすき間が埋まるケースも多いため、すぐに治療が必要とは限らないのです。
ただし、すきっ歯の原因によっては自然に治りにくく、早めの対応が必要になるケースもあります。
心配な場合は、定期的に歯科で経過を見てもらうと安心でしょう。
子どものすきっ歯は自然に治る可能性も高くはありますが、放っておくのはよくありません。
次のようなリスクもあるため、症状が見られる場合には、早期に歯科医師に相談することをおすすめします。
以下では、それぞれについて詳しく解説します。

前歯にすき間があると、空気がもれやすくなります。
そのため、サ行やタ行の発音が不明瞭になりやすく、舌足らずな話し方になってしまうこともあるでしょう。
コミュニケーションに支障をきたす可能性があるほか、学校生活や友達との会話で気になってしまい、消極的な子になる可能性もあります。
すきっ歯の状態では、歯と歯の間にすき間があるため、食べ物が詰まりやすくなります。
その結果、歯垢(プラーク)がたまりやすくなり、虫歯や歯周病になるリスクが高まります。
お口の中をしっかりとケアする必要がありますが、自分では歯みがきを上手にできない子どもも少なくありません。
口内環境が悪化しやすいため、注意が必要です。


すきっ歯は見た目に影響を与えるため、子どもが成長するにつれてコンプレックスにつながる可能性があります。
特に友だちから指摘されたり、からかわれたりすると、自分の口元に自信を持てなくなり、笑顔を見せるのをためらうようになる場合もあるでしょう。
さらに、思春期に入ると自らの見た目を気にするようになり、すきっ歯をコンプレックスに感じる子どもも少なくありません。
見た目に自信をもてず、消極的になってしまう可能性もあります。
子どものすきっ歯を治療する主な方法としては、以下の3つが挙げられます。
透明なマウスピースを装着して歯並びを整える治療法です。
痛みが軽く、取り外しも可能なため、子どもにとって負担が少ないのが特徴です。
複雑な症例では適用できない可能性もありますが、すきっ歯など比較的軽度の歯並びの乱れであれば、対応できるケースが多いでしょう。
また、食事や歯みがきの際に取り外せるため、口腔内を清潔に保ちやすいというメリットもあります。
ただし、装着時間を守らないと効果が出にくいため、本人の協力が不可欠です。
適応できるかどうかは症例によるため、まずは歯科医師に相談してみましょう。
POINT
MFT(Myofunctional Therapy)は、指しゃぶりや前歯を押し出す舌癖、口呼吸など、すきっ歯の原因となる悪習慣がある場合に用いる方法です。
舌や唇、頬など口のまわりの筋肉を正しく使えるようにトレーニングするほか、正しい舌の位置を記憶させたり、鼻呼吸を促したりするなど、悪癖の改善を行います。
矯正治療と併用すれば、後戻りの予防も期待できます。
床矯正(しょうきょうせい)は、取り外し可能な矯正装置を使って、あごの骨を少しずつ広げ、歯がきれいに並ぶスペースを作る治療法です。
すきっ歯に限らず、歯列不正やかみ合わせの改善にも用いられます。
特に成長期の子どもに適しており、あごの成長を利用して自然な歯並びへと導けるのが特徴です。
ワイヤー矯正に比べて痛みが少なく、学校や食事のときは外せるため、日常生活への影響も最小限に抑えられます。
※当院では対応しておりません。

子どものすきっ歯の治療を開始するタイミングは、原因や程度によって異なります。
ただし、自然に改善する可能性もあるため、永久歯が生えそろう10〜12歳頃までは経過観察となるケースが多いでしょう。
しかし、原因によっては、早期に治療を開始するのが賢明です。
特に6〜8歳ごろは、あごの成長を利用して治療できるため、治療が必要な場合は、開始に適した時期といえます。
すきっ歯が気になる場合は、早めに専門医に相談し、適切なタイミングを見極めてもらうことをおすすめします。
Contact
ご予約・お問い合わせ

調布歯科・かおいく矯正歯科では、歯並びを悪化させる根本的な原因に対してアプローチを行う新しい小児矯正歯科治療「顔育矯正」を実施しております。根本的な原因を取り除くため、治療後も後戻りしづらいのが特徴です。また、小児期は顎の成長過程にあるため、歯並びと共にお顔立ちにも良い影響を及ぼします。

お子様の歯の矯正を検討される上で、実際にどれくらい費用がかかるか気になる方も多いかと思います。子どもの矯正(小児歯科矯正)では、治療を始めるタイミングや選択する治療内容によって異なります。この記事では、治療をはじめるタイミングおよび種類別にどれくらいの費用がかかるのか、また治療費を抑える方法について詳しく解説します。

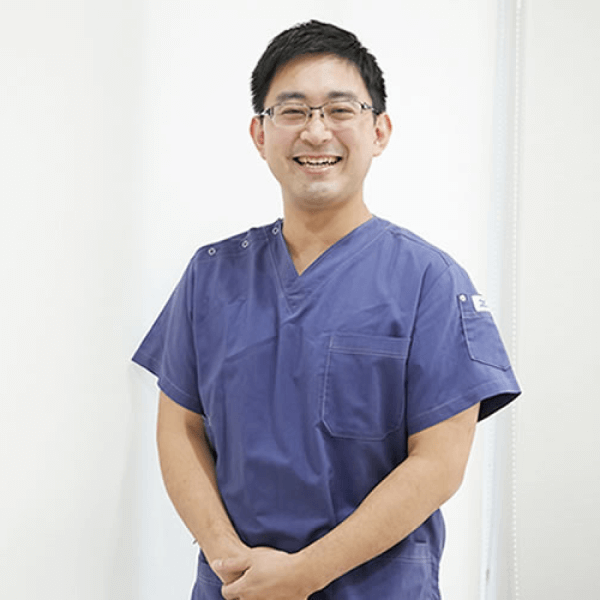
私は東京歯科大学卒業後、なるべく歯を削らないMI治療、マイクロスコープを使用した保存治療、成功率の高い精密根管治療に特化して研鑽を積んでまいりました。解剖講座で研究し博士号を習得したのち、当院の本院にあたる柳沢歯科医院で精密根管治療、保存治療における技術を更に磨いてきております。
また、当院では矯正歯科治療を専門とする歯科医師も在籍し、表側ワイヤー矯正をはじめ、これまでの矯正歯科とは全く異なるアプローチとして顔面骨格の正しい発育を促す小児矯正歯科治療「顔育矯正」にも力を入れております。
「歯をなるべく削らない」「虫歯を取り残さない」「根管治療を成功させる」ことを大切にし、当院のコンセプトとして掲げている”歯医者を卒業するための歯医者”を体現してまいります。
© 調布歯科・かおいく矯正歯科