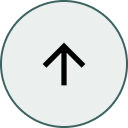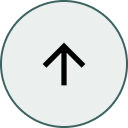調布歯科・かおいく矯正歯科では、歯並びを悪化させる根本的な原因に対してアプローチを行う新しい小児矯正歯科治療「顔育矯正」を実施しております。根本的な原因を取り除くため、治療後も後戻りしづらいのが特徴です。また、小児期は顎の成長過程にあるため、歯並びと共にお顔立ちにも良い影響を及ぼします。

ホーム » 矯正歯科治療 » 小児矯正(子どもの矯正歯科治療) – 顔(顎)の成長を育む顔育矯正 » 子どもの受け口(反対咬合)は治療すべき?
「子どもが受け口(反対咬合)のようで気になるけれど、治療は必要なの?」
「自然に治る可能性もあるって聞いたけど、やっぱり治療すべき?」
など、子どもの受け口が気になっている親御さんもいらっしゃるでしょう。
子どもの受け口は、2歳くらいまでであれば自然に治るケースもあるといわれています。しかし、その割合は10〜15%程度と多くはありません。
症状がみられる場合は、骨格の成長を活かした矯正治療が可能なうちに専門の歯科医師に相談するのが望ましいといえます。

噛み合わせが正常だと、上の前歯がわずかに前に出て、下の歯に重なるものです。
これが逆転し、かみ合わせたときに、下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態を「受け口(反対咬合)」といいます。
見た目が気になるだけでなく、発音が不明瞭になったり、食べ物が噛みにくくなったりといったリスクもあり、軽視はできません。
特に子どもの場合は、顎の骨の成長に影響し、顔つきや将来の歯並びにも関係するため、注意が必要です。
2歳くらいまでであれば、自然に治るケースもある一方で、放置すると矯正が難しくなる可能性もあるため、早期に発見し、適切な治療を開始するのが望ましいといえます。
また、受け口には下記の2つのタイプがあり、どちらに当てはまるかによって治療法や治療の難易度が異なります。
| 骨格的な問題で受け口になるタイプ | 上顎の成長が不十分、または、下顎が過剰に発達していることが原因 |
| 歯の生え方の問題で受け口になるタイプ | 上の前歯が内向きに生えていたり、下の前歯が外向きに生えていたりしていることが原因 |
POINT

受け口になる主な原因としては、下記の5つが挙げられます。
以下では、それぞれについて詳しく説明します。
口を閉じたとき、上顎に軽く触れる位置というのが本来の舌の正しい位置(スポット)です。
しかし、正しい位置よりも常に下方にある「低位舌(ていいぜつ)」になると、下顎が必要以上に成長し、受け口になる可能性があります。
低位舌は、口呼吸や舌の筋力低下、おしゃぶりなどの悪習慣が原因で起こる症状です。
他に、舌の癖によって受け口となるケースもあります。
具体的には、舌で下の前歯を押し出す癖があると、頻繁に下顎へ力が加わるためにその成長を過剰に促してしまいます。
その結果、上顎と下顎の大きさのバランスが取れなくなり、受け口を引き起こしやすくなるのです。
指しゃぶりや頬づえなどの日常的な習慣が原因で受け口になる可能性もあります。
指しゃぶりをすると、舌が正常な位置よりも下がった状態が継続します。
そのため、「低位舌」の症状を引き起こしやすく、下顎の成長に影響した結果、受け口を引き起こす可能性があるのです。
また、頬づえは、顎に対して片側から強い圧力がかかった状態です。
頬杖をつく習慣があり、片側の顎骨に対してのみ頻繁に力をかけていると、バランスが崩れやすくなります。
その結果、下顎が前に出て受け口になりやすくなるのです。
柔らかいものばかり食べていると、噛む回数が少なくなり、顎が十分に使われません。
その結果、顎の筋肉や骨の発達が不十分になり、上下の顎のバランスが崩れてしまう可能性があります。
特に、上顎の成長が遅れると、相対的に下顎が前に出ているように見えやすくなり、受け口になりやすくなります。
前歯で爪を噛む癖があると、前歯に継続的な力を加えることになります。
歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼしやすく、特に下の前歯に強い力がかかると、下顎が前に出やすく、受け口になりやすいでしょう。
爪を噛む癖は精神的なストレスや緊張からくる場合も多いため、単純にやめさせようとするだけでなく、子どもの心の状態にも目を向けることが大切です。

子供に受け口(反対咬合)の症状が見られる場合は、早めに治療を開始することをおすすめします。
早期に治療を開始すれば、次のようなメリットが期待できるからです。
以下では、それぞれについて詳しく説明します。
成長期の子どもは骨がまだ柔らかいため、顎の成長に合わせた矯正治療が可能です。
歯を移動させるためのスペースを無理に確保する必要がなく、抜歯をせずに済む可能性が高いでしょう。
一方、大人になってから受け口を治そうとすると、歯並びのスペースが足りなければ抜歯をしなければなりません。
外科的な手術が必要になるケースもあり、大きな負担がかかる可能性もあるでしょう。
子どものうちに治療を始めれば、痛みなどの負担が少なく済むだけでなく、治療にかかる費用の負担も軽減できます。
受け口の治療を始めれば、指しゃぶりや舌の使い方、頬づえ、爪を噛むといった悪習慣を早めに改善できる可能性もあります。
単に歯並びや骨格の矯正だけをしても、受け口の原因となる子どもの癖を改善しなければ、後戻りをするリスクがあり、根本的な治療にはなりません。
そのため、受け口の治療においては、子どもの癖にも着目し、その改善も同時に進めます。
子どもの受け口が、単なる歯並びの問題だけでなく、骨格のバランスに関係している場合は、矯正治療によってその改善も期待できます。
特に成長期の子どもは骨がまだやわらかく、発育途中であるため、適切に治療すれば無理なく骨格のバランスを整えられます。
大人のように抜歯や外科手術をしなくても、改善できる可能性が高いでしょう。

子どもの受け口(反対咬合)を治療する主な方法としては、以下の3つが挙げられます。
それぞれの方法について解説します。
床矯正(しょうきょうせい)は、上顎が小さいために受け口になっている場合に有効な矯正方法です。
取り外し可能な装置を使って、顎の骨の成長を促しながら下顎とのバランスを無理なく整えます。
装置についたネジを少しずつ回して、上顎をゆっくり広げるので、痛みも少なくてすむでしょう。
装着時間は1日12〜14時間程度で、主に就寝中や自宅で過ごす時間に付けておきます。
学校に行くなど人前に出る際には外してよく、食事や歯磨きの際にも取り外せるので、本人の負担も軽くてすむでしょう。
ただし、決められた装着時間を守らなければ、効果は期待できません。
子どものやる気や保護者のサポートが大切といえるでしょう。
急速拡大装置は、上顎の幅を短期間で広げるための固定式の矯正装置です。
床矯正と同様に、受け口の原因が上顎の成長が不十分な場合に用いられる矯正方法で、中央にあるネジを少しずつ回して力を加え、上顎を左右に拡大します。
まだ骨が柔らかい成長期の子どもにしか適用できない方法で、適応年齢は思春期くらいの年齢までです。
床矯正との大きな違いは、取り外しができないことです。
装置が口の中で固定される分、歯や顎に常に力がかかるため、短期間での成果が見込めます。
一方、装置の装着によって多少の違和感や話しづらさを感じるほか、多少の痛みがある可能性もある点はデメリットといえるでしょう。
マウスピースを使って歯並びを少しずつ整えていく治療法です。
装置は透明であるため、装着していても目立ちにくく、違和感も少ないため、学校生活においても支障をきたしにくいでしょう。
取り外して食事や歯磨きができるため、衛生的なのもメリットです。
子どもの受け口治療で、よく用いられるのが「プレオルソ」や「ムーシールド」といった子ども専用のマウスピース型矯正装置です。
ムーシールドは3歳ごろから使用可能な装置で、舌の位置や口周りの筋肉バランスを整え、受け口の改善を促します。
一方、プレオルソは、正しい歯並びに誘導するとともに噛み合わせや呼吸の改善も目的とした装置です。
どちらも就寝時と在宅時に装着するだけで済むうえ、骨の成長を利用しながら治療するため、痛みも少なくてすみます。
ただし、装着時間を守るなど正しく適用しなければ、十分な効果は得にくいため、本人の協力が不可欠です。
また、症状によっては他の方法の併用が必要になるケースもあります。
POINT
子どもの受け口の治療期間は、一般的には1〜3年程度が目安です。
症状の程度や使用する装置によって異なり、各治療方法の治療期間は以下が目安になります。
| 治療方法 | 治療期間の目安 |
|---|---|
| 床矯正 | 2〜3年程度 |
| 急速拡大装置 | 3ヵ月〜6ヵ月程度 |
| マウスピース矯正 | 1〜3年程度 |
Contact
ご予約・お問い合わせ

調布歯科・かおいく矯正歯科では、歯並びを悪化させる根本的な原因に対してアプローチを行う新しい小児矯正歯科治療「顔育矯正」を実施しております。根本的な原因を取り除くため、治療後も後戻りしづらいのが特徴です。また、小児期は顎の成長過程にあるため、歯並びと共にお顔立ちにも良い影響を及ぼします。

お子様の歯の矯正を検討される上で、実際にどれくらい費用がかかるか気になる方も多いかと思います。子どもの矯正(小児歯科矯正)では、治療を始めるタイミングや選択する治療内容によって異なります。この記事では、治療をはじめるタイミングおよび種類別にどれくらいの費用がかかるのか、また治療費を抑える方法について詳しく解説します。

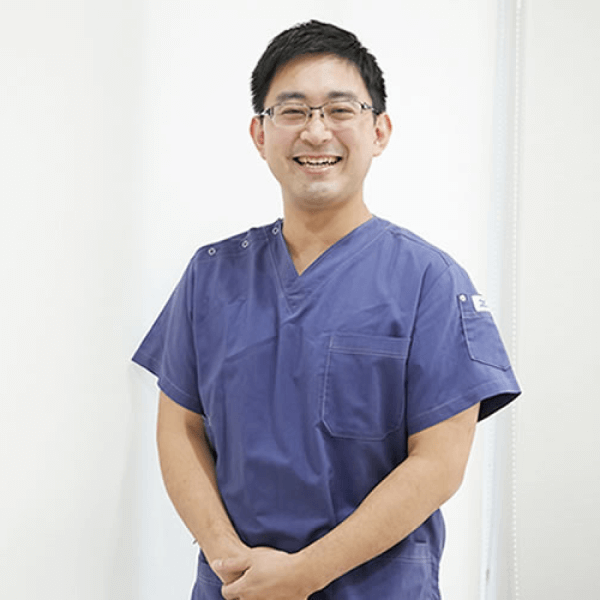
私は東京歯科大学卒業後、なるべく歯を削らないMI治療、マイクロスコープを使用した保存治療、成功率の高い精密根管治療に特化して研鑽を積んでまいりました。解剖講座で研究し博士号を習得したのち、当院の本院にあたる柳沢歯科医院で精密根管治療、保存治療における技術を更に磨いてきております。
また、当院では矯正歯科治療を専門とする歯科医師も在籍し、表側ワイヤー矯正をはじめ、これまでの矯正歯科とは全く異なるアプローチとして顔面骨格の正しい発育を促す小児矯正歯科治療「顔育矯正」にも力を入れております。
「歯をなるべく削らない」「虫歯を取り残さない」「根管治療を成功させる」ことを大切にし、当院のコンセプトとして掲げている”歯医者を卒業するための歯医者”を体現してまいります。
© 調布歯科・かおいく矯正歯科