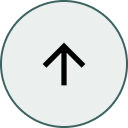【子どもの出っ歯でお悩みの方必見!】子どもの出っ歯の原因やリスク、治療法について解説
ホーム » 矯正歯科治療 » 小児矯正(子どもの矯正歯科治療) – 顔(顎)の成長を育む顔育矯正 » 【子どもの出っ歯でお悩みの方必見!】子どもの出っ歯の原因やリスク、治療法について解説
「うちの子、前歯が出てきたかも…」「乳歯だし放っておいてもいいのかな」などと、子どもの歯並びについて気になっている親御さんもいるでしょう。
いわゆる「出っ歯(上顎前突)」とは、上の歯が下の歯よりも前に出過ぎている状態をいいます。
放っておくと、見た目の問題だけでなく、むし歯や噛み合わせの悪化といったリスクがあるため、早期に適切な治療を受ける必要があります。
本記事では、子どもの出っ歯の原因や放置によって生じるリスク、治療法、予防法について解説します。
子どもの健やかな成長をサポートするためにも、正しい知識を身につけましょう。
子どもの出っ歯(上顎前突)とは?
「出っ歯」とは、上の前歯が下の前歯よりも大きく前に突き出ている状態をいいます。
医学的には「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」と呼ぶ症状です。
もっとも気になるのは見た目の問題かもしれませんが、歯や口の健康、発音や咀嚼機能にも影響を及ぼす可能性があるため、軽く考えるのは禁物です。
特に子どもの場合は、骨格や歯が成長途中であるため、早めに気づいて対処すれば、将来的なトラブルを未然に防げる可能性が高いでしょう。
特に次のような症状が見られる場合は、出っ歯と診断される可能性があります。
歯科医師に相談し、適切な治療を開始するのが望ましいでしょう。
- 前歯が大きくて目立つ
- 上下の前歯が噛み合っていない
- 口が閉じづらい
- 口呼吸をしている
- うまくものを噛めない
子どもの出っ歯の原因

子どもが出っ歯になる主な原因としては次のようなものが挙げられます。
- 遺伝
- 口呼吸の習慣
- 舌の位置が前方にある
- 唇を閉じる力が弱い
- 指しゃぶりが長期間続く
- 柔らかいものばかり食べる
以下でそれぞれについて詳しく説明します。
遺伝
顔や外見の特徴が親から子どもへ受け継がれていくように、歯並びも遺伝するものです。
歯の大きさや並び方だけでなく、あごの大きさやバランスなどが遺伝する可能性もあります。
特に次のような特徴が見られる場合は、遺伝が原因の出っ歯である可能性があります。
- 上あごが前に出ている
- 下あごが小さい
親や祖父母に上顎前突の方がいる場合は、特に遺伝が原因である可能性が高いと考えられるでしょう。
口呼吸の習慣
口呼吸が習慣になると、口の中では常に舌が下がった状態になるために、上あごの正しい成長が妨げられてしまいます。
さらに、口が開いた状態のままになりやすく、唇から歯を抑える力もかかりにくくなるため、前歯が前方に押し出されやすくなるのです。
子どもが口呼吸になってしまう主な原因としては以下が挙げられます。
- アレルギー性鼻炎などによる鼻づまり
- 扁桃肥大
- あごの発達の問題
このような症状が見られる場合は特に注意しましょう。
舌の位置が前方にある(舌突出癖)
舌の位置が常に前方にある「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」も、出っ歯になりやすい習慣のひとつです。
舌の位置は上あごの内側に軽く触れるところにあるのが自然です。
しかし、舌が前方にあると、前歯に対して内側から押す力が常に加わるため、前歯が突き出てしまいやすくなります。
特に、飲み込むときや言葉を発するときに、舌で前歯を押す癖がある子どもは要注意です。
癖として定着しやすいため、早期に歯科医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。
唇を閉じる力が弱い
唇を閉じる力が弱いことも、出っ歯になりやすい原因のひとつです。
通常、口を閉じたとき、前歯には唇から内向きの力がかかります。
しかし、唇の筋力が弱いと、前歯に対する力が適切にかかりません。
前歯には舌の圧力など外に押し出す力もかかるため、外に押し出す力の方が勝ってしまいます。
その結果、前歯は前に押し出されてしまい出っ歯になってしまうのです。
特に口をぽかんと開けている時間が長い子どもは、この傾向が強くなるため注意しましょう。
指しゃぶりが長期間続く
指しゃぶりも、子どもの出っ歯の原因となります。
3歳くらいまでの指しゃぶりは、子どもの自然な行動であり、歯並びに対する影響は大きくはありません。
しかし、3歳以降も習慣的に続けているなら注意が必要です。
指しゃぶりをすると、指を吸う力や指の力が上の前歯に継続的にかかり、前歯が前方に押し出されて出っ歯になってしまう可能性があるからです。
また、指しゃぶりはあごの成長バランスや噛み合わせにも悪影響を与える可能性があります。
4歳を過ぎても続く場合は特に注意しましょう。
柔らかいものばかり食べる食習慣
柔らかいものばかりを食べていると、噛む回数が少なくなり、あごが十分に発達しません。
その結果、歯が正しく並ぶためのスペースが確保されず、前歯が前方に押し出されて出っ歯になってしまう可能性があります。
噛む力も十分に発達せず、口まわりの筋肉や唇の力も発達しにくくなるため、出っ歯を助長しやすくなります。
歯並び全体に影響する可能性もあるため、注意が必要です。
子どもの出っ歯を放置するリスク
「前歯が気になるけど、乳歯だし、まだ放っておいてもいいかな」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、子どもの出っ歯を放置すると、以下のようなリスクがあります。
速やかに歯科医師に相談しましょう。
- むし歯
- 歯周病になりやすくなる
- 発音がうまくできず滑舌が悪くなる
- 噛み合わせが悪化して食事しにくくなる
- コンプレックスにつながる
以下では、それぞれについて解説します。

むし歯・歯周病になりやすくなる
前歯が突出すると、上の歯と下の歯が正しく噛み合わないために口を閉じにくくなります。
すると、口の中が乾燥しやすくなり、唾液による自浄作用が弱まります。
その結果、歯の表面に汚れや細菌がたまりやすくなり、むし歯や歯ぐきの炎症が起こりやすくなるのです。
また、歯並びが乱れていると、歯ブラシが届きにくく、しっかりと磨けない部分が出てきます。
これもむし歯や歯周病になりやすい原因となり得ます。
発音がうまくできず滑舌が悪くなる
出っ歯になると、上の前歯と下の前歯の間にすき間ができるために、空気が漏れやすくなります。
さらに舌が正常な位置に留まりにくく、動きも変わるために、発音しにくい音が生じるでしょう。
特に「さ行」や「た行」の発音が難しく、滑舌が悪く聞こえるかもしれません。
コミュニケーションが取りにくいために自信をなくしたり、人前で話すことに抵抗を感じたりするようになる可能性もあります。


噛み合わせが悪化して食事しにくくなる
本来、人は上下の前歯によって食べ物を噛み切ります。
しかし、前歯が前方に突き出て、上下の歯がうまくかみ合っていなければ、しっかり噛み切れません。
その結果、食べ物を十分に小さくしないまま飲み込んでしまう癖がつき、消化不良を起こすリスクがあります。
さらに、前歯をうまく使えないために、奥歯で咀嚼する癖が付きやすい点も問題です。
奥歯ばかりで噛んでいると、奥歯やあごの骨に負担が集中し、痛みや疲れの原因になる可能性もあります。
将来的に奥歯を失ってしまうリスクもゼロではありません。
コンプレックスにつながる
出っ歯は見た目にわかりやすいため、子どもがコンプレックスを抱く可能性があります。
特に、友達から容姿についてからかわれたり、思春期になって自分の容姿が気になったりすると、人前で話したり笑ったりすることを避けるようになるかもしれません。

子どもの出っ歯の治療法
主な子どもの出っ歯の治療方法には、以下の3つがあります。
- 床矯正
- 急速拡大装置
- マウスピース矯正
それぞれについて解説します。
床矯正
床矯正(しょうきょうせい)とは、取り外し可能な装置を使って、あごの成長を促しながら歯並びを整える矯正治療です。
主に成長期の子どもに適用する治療方法で、上あごの狭さや歯のスペース不足を改善することで出っ歯を改善します。
食事や歯磨きのときには取り外せるため、負担が少なく、虫歯になりにくいのが特徴です。
装置のネジを少しずつ調整してあごを広げていくため、痛みも少ないでしょう。
ただし、装着時間を管理せねばならなかったり、後戻りする可能性があったりする点には注意が必要です。
将来的に本格的な矯正が不要になるケースもあるため、早期の相談がおすすめです。
急速拡大装置
主に上あごの幅を短期間で広げるための固定式の矯正装置です。
上あごの中央にあるネジを定期的に回して骨を左右に押し広げ、歯が並ぶスペースを確保することで出っ歯を改善します。
床矯正と似ていますが、床矯正が取り外し式でゆっくり進めるのに対し、急速拡大装置は取り外しができず、比較的強い力で短期間に広げる点が大きな違いです。
特に骨の柔らかい6〜12歳頃に適しており、重度の出っ歯やスペース不足に対して効果的です。
違和感や痛みが出る場合もあるため、使用中は歯科医師によるこまめなフォローが必要です。
マウスピース矯正
マウスピース矯正は、透明で取り外し可能な装置を使って、少しずつ歯を動かしていく矯正方法です。
見た目が目立ちにくく、金属の装置に比べて違和感や痛みが少ないのが特徴です。
子どものマウスピース矯正では、「インビザライン・ファースト」など、成長期に対応した専用の装置もあり、出っ歯の改善に効果が期待できます。
食事や歯磨きの際に取り外せるため、衛生的に使えるのもメリットです。
ただし、1日20時間以上の装着が必要なため、本人の協力が欠かせません。
出っ歯の程度によっては他の治療と併用する場合もあります。
POINT
顔育矯正とは、歯並びが悪化する原因を改善し正しい歯並びへと導く治療です。
顎の成長段階である12歳頃までの時期に治療を行い、永久歯が生え揃ってからの治療を不要とすることを目的としています。
こどもの出っ歯矯正は何歳から?

子どもの出っ歯の矯正治療は、一般的に6〜8歳頃から始めるのが望ましいとされています。
この時期は、あごの骨が柔らかく成長段階にあるため、矯正による効果が出やすいためです。
早期に治療を始めれば、適切なあごの成長を促し、将来的に本格的な矯正を避けられる可能性も高まります。
出っ歯の程度がひどくても永久歯を抜かずにきれいな歯並びを手に入れられることも少なくありません。
子どもの出っ歯が気になる場合は、8歳頃には矯正歯科医師に相談しましょう。
子どもの出っ歯の予防法
出っ歯になってしまったら、自力では改善できません。
予防には、原因となる悪い習慣や癖を改善したり、噛む力を養って口の周りの筋肉を鍛えたりすることが大切です。
方法1
出っ歯を予防するうえで大切なのが、「原因となる悪い習慣や癖をやめさせる」ことです。
以下では、主な癖と対策をまとめました。
| 出っ歯の原因となる習慣・癖 | 対策 |
|---|---|
| 4歳以降の指しゃぶり |
・手を握る ・手や指を使った遊びをする ・指に絆創膏をまく ・指しゃぶり防止用の塗り薬を使う |
| 舌を前歯に押し付ける |
・よくない癖だと知ってもらう ・舌のトレーニングをする ・矯正装置を使用する |
| 口呼吸 |
・鼻呼吸をするよう意識してもらう ・就寝時に市販のテープを貼る ・口周りの筋肉を鍛える体操をする ・耳鼻科や小児科を受診し、根本的な原因となっている症状を治療する |
これらの癖に早い段階で気づき、対応すれば、出っ歯の進行を防げます。
日頃から子どもの様子をよく観察し、必要に応じて改善しましょう。
方法2
出っ歯を予防するには、「噛む力を養う」ことも非常に重要です。
現代の食生活では、柔らかいものを食べる傾向が強く、噛む回数が減少しがちです。
しかし、しっかり噛む習慣がなければ、あごの骨が十分に成長せず、歯が並ぶスペースが確保できないために、出っ歯になりやすいでしょう。
そのため、食事においては、繊維質の多い野菜や、少し噛みごたえのある食材をうまく取り入れたいところです。
3歳頃からは少し固い果物を、4歳頃からは根菜類を食べさせるなど柔らかいものばかり食べさせないよう心がけましょう。
自然と噛む回数を増やしてよく噛む習慣を育てれば、出っ歯予防だけでなく全身の健康にも良い影響を与えられます。
方法3
出っ歯の予防には、「むし歯の治療をきちんと行う」ことも大切です。
「乳歯なら生え変わるから放っておいても大丈夫なのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、放置は禁物です。
虫歯が悪化して、早くに乳歯を失ってしまうと、周囲の歯がそのスペースを埋めようと動くために、歯並びが乱れて出っ歯につながりやすくなります。
特に乳歯は将来の永久歯の位置を導く役割もあるため、早期に抜けてしまうと、将来的な歯並びに悪影響を及ぼします。
また、痛みなどで噛む位置が偏れば、あごのバランスを崩す原因にもなりかねません。
出っ歯を予防するためにも、定期的に歯科検診を受けて、早期発見、早期治療を心がけましょう。
まとめ
その原因は、遺伝のほか、口呼吸や指しゃぶり、柔らかいものばかり食べる習慣など、生活習慣の影響が大きくあります。
成長期の子どもであれば、骨が柔らかいため、骨格の成長を利用して治療することもできます。
早期に治療を開始できれば、本人の負担は少なく、歯並びを美しく整えられる可能性が高まります。
成長期以降に本格的な矯正が不要になる場合もあり、経済的・身体的な負担を軽減できるケースも少なくないでしょう。
子どもの出っ歯が気になる場合は、早めに歯科医師に相談することをおすすめします。
関連記事
Contact
ご予約・お問い合わせ
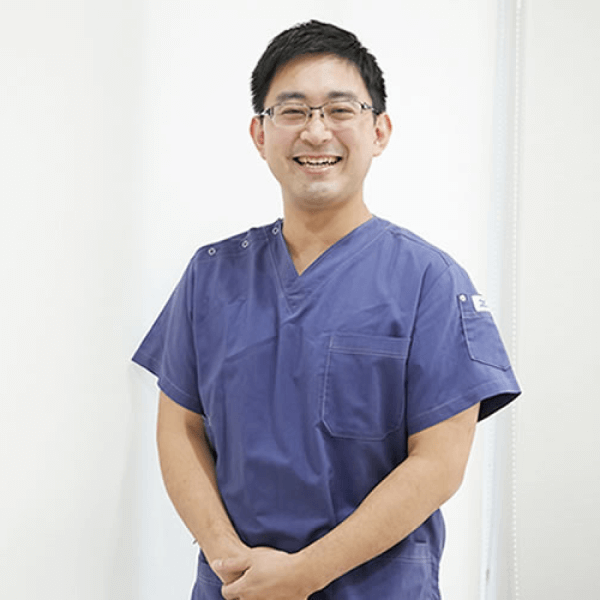
私は東京歯科大学卒業後、なるべく歯を削らないMI治療、マイクロスコープを使用した保存治療、成功率の高い精密根管治療に特化して研鑽を積んでまいりました。解剖講座で研究し博士号を習得したのち、当院の本院にあたる柳沢歯科医院で精密根管治療、保存治療における技術を更に磨いてきております。
また、当院では矯正歯科治療を専門とする歯科医師も在籍し、表側ワイヤー矯正をはじめ、これまでの矯正歯科とは全く異なるアプローチとして顔面骨格の正しい発育を促す小児矯正歯科治療「顔育矯正」にも力を入れております。
「歯をなるべく削らない」「虫歯を取り残さない」「根管治療を成功させる」ことを大切にし、当院のコンセプトとして掲げている”歯医者を卒業するための歯医者”を体現してまいります。